はじめに
空を飛ぶ無人の機体「ドローン」。今日では様々な分野で活用されているこの技術ですが、その起源は意外にも古く、1930年代にまでさかのぼります。とりわけ日本では、1980年代から農業分野でのドローン活用が進められ、世界に先駆けて産業用無人ヘリコプターが実用化されてきました。
幅広い用途で活躍する現代のドローン。その技術はどのようにして発展し、私たちの生活に浸透してきたのでしょうか。ドローンの歴史を振り返りながら、その魅力と可能性に迫ります。

空を飛ぶ無人の機体「ドローン」。今日では様々な分野で活用されているこの技術ですが、その起源は意外にも古く、1930年代にまでさかのぼります。とりわけ日本では、1980年代から農業分野でのドローン活用が進められ、世界に先駆けて産業用無人ヘリコプターが実用化されてきました。
幅広い用途で活躍する現代のドローン。その技術はどのようにして発展し、私たちの生活に浸透してきたのでしょうか。ドローンの歴史を振り返りながら、その魅力と可能性に迫ります。
ドローンとは、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができる無人航空機のことを指します。国土交通省の定義によると、「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量のものを除く)」とされています。多くの人がイメージするドローンはマルチコプター型ですが、実はドローンの定義にはヘリコプター型や飛行機型も含まれるのです。
「ドローン」という名称の由来には、主に2つの説があります。
1つ目は、プロペラを高速回転させて飛ぶ際に発生する「ブーン」という音が、蜂の羽音に似ていることから、英語で「雄蜂」を意味する「drone」と名付けられたという説です。
2つ目は、1935年にイギリスで開発された無人標的機「クイーンビー」(Queen Bee、女王蜂の意味)に敬意を表して、アメリカが「drone」(雄蜂)という名称を採用したという説です。
どちらの説が正しいかは定かではありませんが、蜂にちなんだ名称であることは間違いないようです。
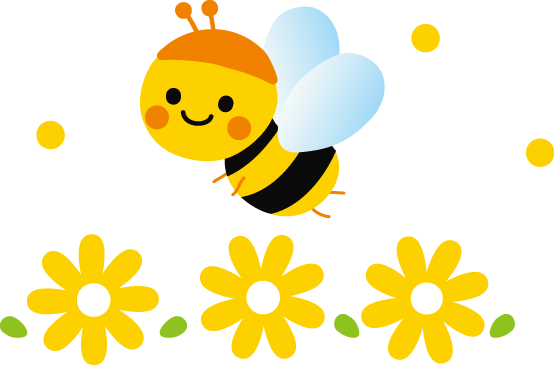
ドローンのルーツは、第二次世界大戦前後の軍事技術にさかのぼります。1935年、イギリスは世界で初めて無人飛行機「クイーンビー」の飛行に成功しました。これは、練習機デハビランド・タイガーモスに無線誘導装置を搭載した無人機で、対空射撃訓練用の標的として使用されました。非常に安定した性能を持ち、1935年から約380機が生産され、1947年まで英国の空軍と海軍で使用されていました。

アメリカも1940年代に無人飛行機の開発に成功し、その後も軍事目的での開発が進められました。当時は搭載した爆弾を爆発させて敵機を撃墜することを目的としていましたが、技術的な制約から操縦不能になるケースも多く、実際の戦場で使用されることはほとんどありませんでした。
冷戦時代には、特に偵察任務のための無人機開発が進みました。有人機では危険な敵地の情報収集を、無人機なら安全に行える利点が重視されたのです。高精度なカメラやセンサー技術の導入により、無人機の偵察能力は飛躍的に向上しました。
1980年代になると、半導体技術や電子機器の進化により、ドローンの小型化や低価格化が進み、民間でも産業用ドローンが活用されるようになりました。特に注目すべきは、日本が世界に先駆けて農業分野でのドローン活用を進めたことです。
1987年、ヤマハ発動機は世界初の産業用無人ラジコンヘリコプター「R-50」を発売しました。見た目はヘリコプターですが、無人で操縦されるため、現在の定義ではドローンに分類されます。
この「R-50」は、20kgの薬剤を積載できる能力を持ち、日本の水田での農薬散布に革命をもたらしました。その後、ヤマハは改良を重ね、1997年には2代目となる「RMAX」を発売。RMAXには10個のCPUが搭載され、常に運転状況を把握し、異常があっても安全に制御できる機能が付加されました。

日本の農業分野でのドローン活用は非常に成功し、2000年代には国内に2,600機以上の農薬散布用無人ヘリコプターが登録されるまでになりました。日本はまさに「ドローン大国」だったのです。
2010年代に入ると、ドローン技術は一般消費者にも普及し始めました。マルチコプター型のドローンが登場し、農薬散布だけでなく、様々な用途に活用されるようになったのです。
2010年、フランスのParrot社が発売した「AR Drone」は、スマートフォンで操作できる手軽さが話題を呼び、消費者市場でのドローン普及の大きな契機となりました。
「AR Drone」はWi-Fiでスマートフォンに接続し、専用アプリを使って操縦できるという画期的な仕様でした。また、搭載されたカメラからの映像をリアルタイムで見ながら操縦できるFPV(First Person View)機能も備えていました。

2012年には、現在もドローン市場で最大のシェアを持つDJI社が「Phantom 1」を発売。このドローンは、飛行に必要な要素をすべて詰め込んだオールインワンパッケージとして注目を集めました。
「Phantom 1」はカメラ搭載のための台が付属しており、別途用意したカメラを取り付けて空撮を楽しむことができました。その後のモデルではカメラが内蔵されるようになり、より高品質な空撮が容易になりました。

こうした消費者向けドローンの普及により、ドローンは空撮、測量、点検、農業、物流など様々な分野で活用されるようになりました。特に空撮分野では、それまで高額な費用がかかっていた航空写真や映像撮影が、比較的安価に行えるようになり、映像業界に大きな変革をもたらしました。
現在の農薬散布ドローンは、ヘリコプター型からマルチコプター型まで様々な形態があります。ヤマハ発動機の「FAZER R」シリーズや「YMR」シリーズは、長年の経験と技術を活かした高性能な農薬散布ドローンとして、今も日本の農業現場で活躍しています。
最新の農薬散布ドローンには、GPSによる自動飛行機能や、散布量を自動調節する機能、障害物を検知して回避する機能など、高度な技術が搭載されています。これにより、操縦者の負担が軽減され、より安全で効率的な農薬散布が可能になっています。
また、ドローンによる農薬散布は、従来の有人ヘリコプターやトラクターと比べて、作業効率が向上し、燃料消費や排気ガスの削減にもつながるため、環境にも優しい技術として注目されています。
今後は、AIやIoT技術との連携により、さらに高度な自動化や最適化が進むことが期待されます。例えば、センサーで作物の生育状態や病害虫の発生状況を検知し、必要な場所に必要な量の農薬を散布するといった「精密農業」の実現に向けて、ドローン技術は進化し続けるでしょう。
ドローンの歴史は、1930年代の軍事目的から始まり、日本の農業分野での先駆的な活用を経て、現在では様々な産業や一般消費者にまで広がっています。特に日本は、農薬散布用ドローンの開発と普及において、世界をリードしてきました。
テクノロジーの進化とともに、ドローンの性能や機能は飛躍的に向上し、様々な新しい可能性を生み出しています。農薬散布ドローンもまた、日々進化を続け、農業の効率化や省力化、環境負荷の低減に貢献しています。
これからも、ドローンは私たちの生活や産業にさらに深く溶け込み、新たな価値を創造していくことでしょう。